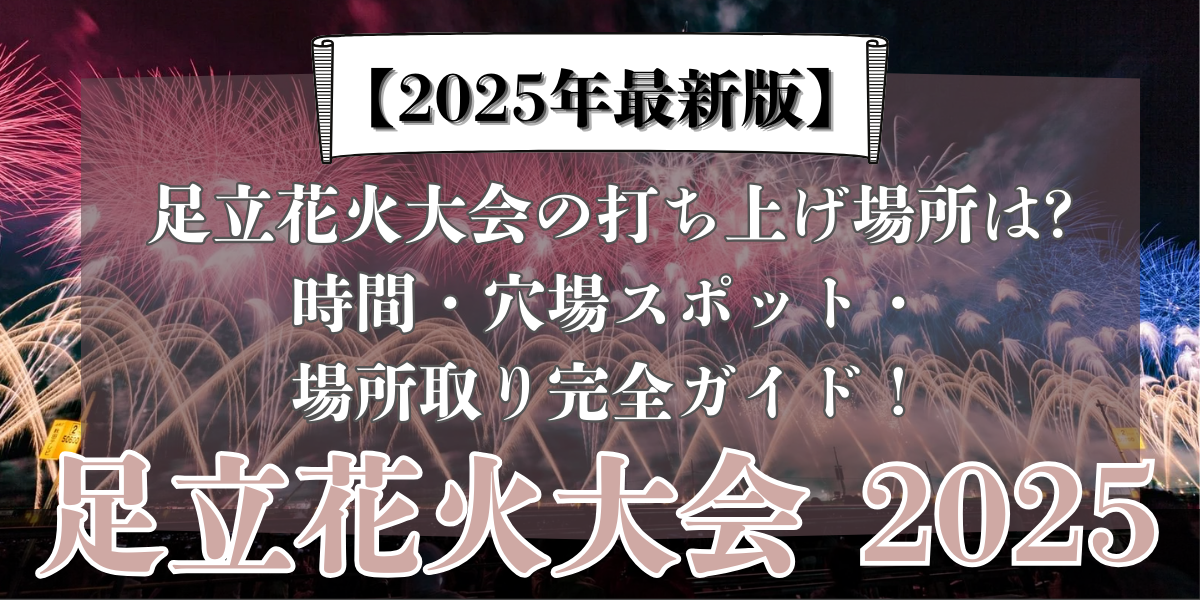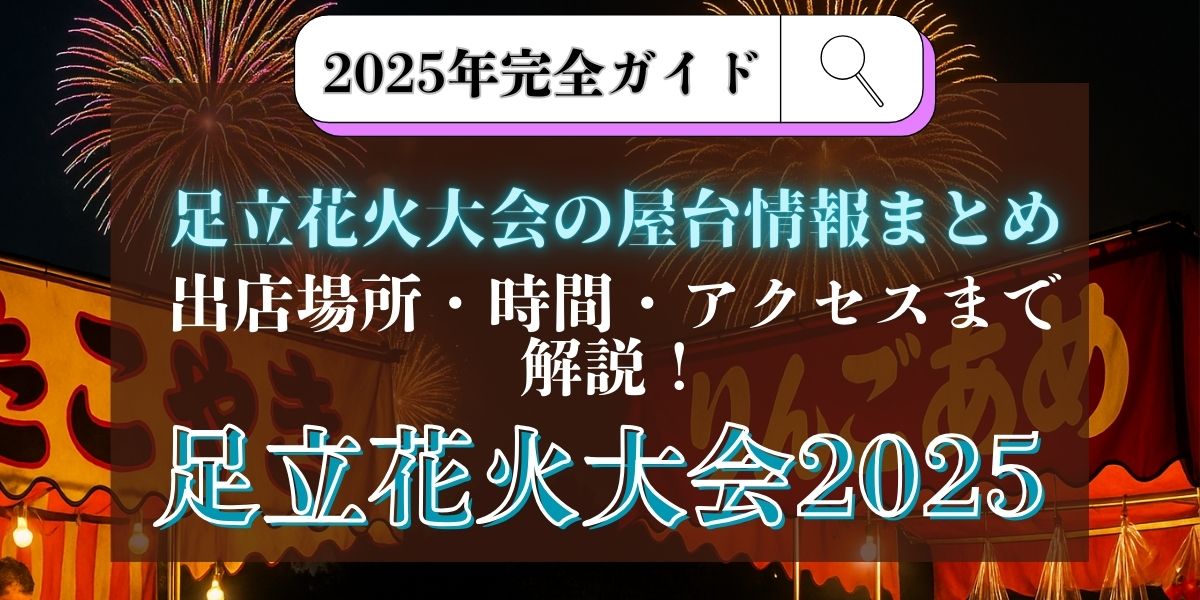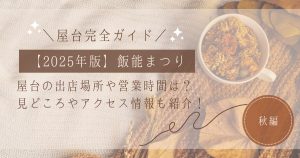足立花火大会の屋台、どこに出るか知っていますか?
「何時からやってる?」
「人気グルメは?」
「混雑を避けるには?」
せっかく行くなら、屋台と花火をどちらも思い切り楽しみたいですよね。
この記事では、そんな疑問を一気に解決!
出店場所・時間・注目グルメに加えて、アクセスや混雑対策までまとめた完全ガイドです。
この記事を読めば、足立花火2025を満喫できますよ!
打ち上げ場所・穴場・場所取りについてはこの記事☟!併せてチェックしてください!
足立花火大会の打ち上げ場所は?時間・穴場スポット・場所取り完全ガイド!【2025年最新版】
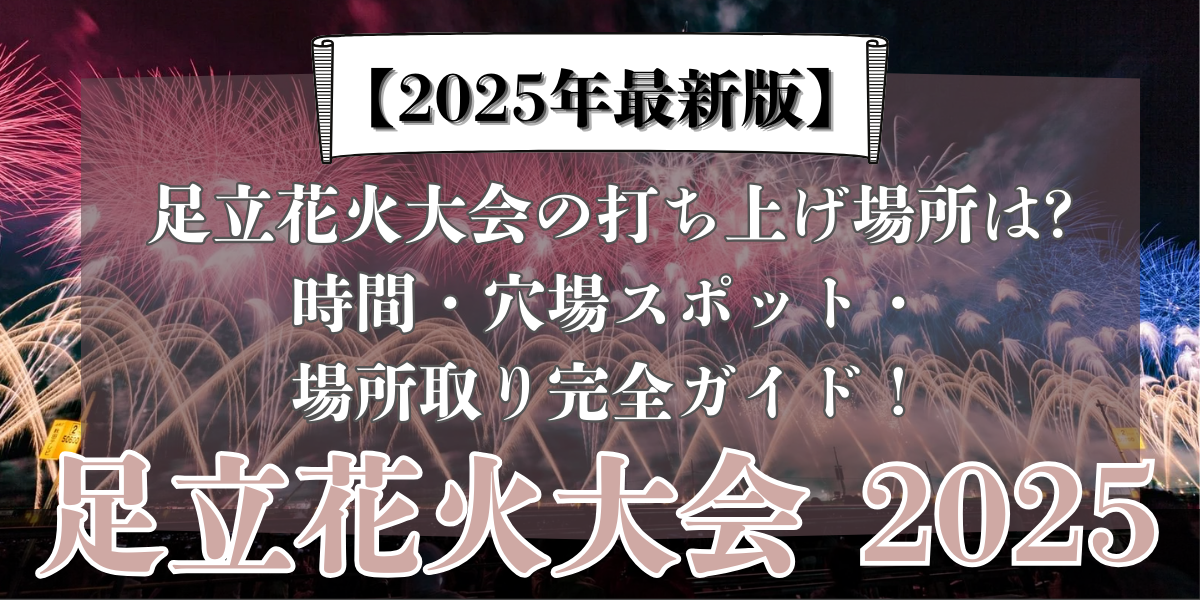

足立花火大会2025|開催日・打ち上げ場所などの基本情報
例年7月に開催されている足立花火大会は、熱中症や荒天を避けるため今年は5月開催になりました。
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開催日 | 2025年5月31日(土) ※荒天時中止 |
| 時間 | 19:20〜20:20(約1時間) |
| 打ち上げ数 | 総数14,010発(13,000発+1,010発) |
| 会場 | 荒川河川敷(東京メトロ千代田線鉄橋〜西新井橋間) |
| 最寄り駅 | 北千住駅、西新井駅、梅島駅、小菅駅 など |
| 有料席 | あり(完売)※詳細は足立区公式サイトにて |
| 例年の来場者数 | 約70万人 |
| 駐車場 | なし(原則公共交通機関で来場) |
| 喫煙所 | 基本的になし(喫煙は駅周辺の指定エリアで) |
毎年、都内最大級の人出を記録する大人気イベントです。
2025年も大変な混雑が予想されるので、アクセス・時間に余裕をもって行動しましょう!
足立花火大会2025の屋台はどこに出る?
ただしご安心を。
足立花火大会では、会場以外の場所で屋台の出店があります!
例年、多くの屋台が並ぶのは以下のような「会場までの道中」や「周辺の歩道沿い」です。
- 北千住駅から荒川河川敷へ向かうルート沿い(特ににぎやか!)
- 西新井駅から土手に向かうルート(やや穴場エリア)
- 千住新橋や西新井橋の付近
このように、会場に向かう道そのものが“お祭り通り”に変わります。
歩きながら屋台を巡る体験も、足立花火大会の大きな魅力です!
屋台は何時から?営業開始時間の目安
例年、屋台の営業開始は15:00〜16:00頃からが目安とされています。
- 17時〜19時がピークタイム
- 人気の屋台は夕方前にはすでに行列あり
- 遅くなると売り切れになるグルメも多数
そのため、16時台には現地に到着しておくのがおすすめです。
花火の時間に近づくほど混雑するので、早めの行動が吉ですよ。
どんな屋台が出る?2025年の傾向と注目グルメ
22025年の出店情報はまだ公式発表前ですが、過去の傾向や最近の屋台事情から以下のような屋台が登場すると予想されます。
✨ 定番グルメ
お祭りといえば!の定番グルメが勢ぞろい!

- たこ焼き
- 焼きそば
- かき氷
- じゃがバター
- 唐揚げ
- 焼き鳥
- 綿あめ
- 餃子
- 鮎の塩焼き
- きゅうり
- あんずあめ
- ケバブ
- ポテト
- ベビーカステラ
- イカ焼き
- チョコバナナ
- お好み焼き
🍭 SNS映え!グルメ
流行りのインスタ映えスイーツや、写真映えする長~いポテトなど!
SNSにあげちゃおう!

- 電球ソーダ
- フルーツ飴
- トルネードポテト
- フルーツ大福
🌶 人気急上昇の韓国系グルメ
韓国グルメは屋台では必須!
本場の雰囲気が楽しめちゃう!

- チーズハットグ
- チヂミ
- キンパ(巻き寿司)
- 10円パン
🎯 子どもに人気の屋台
お祭りと言えば、グルメだけじゃない!
こんなゲーム屋台も!

- くじ引き
- 射的
- スーパーボールすくい
屋台をメインで楽しみたい人は、なるべく17時前に会場周辺へ到着しておくと、行列も避けやすく快適です!
屋台と花火、両方楽しめるおすすめの立ち回り
花火だけでなく屋台も存分に楽しみたいなら、以下のルートがおすすめです
- 🔹 北千住駅からのルート(にぎやかで雰囲気◎)
-
屋台の出店数が多く、にぎやかな雰囲気を味わいたい人におすすめ。
夕暮れのなか、グルメを楽しみつつ花火会場へ向かう“夏のお祭り感”をたっぷり味わえます。
- 🔹 西新井駅〜西新井橋ルート(やや穴場)
-
北千住ほど混雑していないため、比較的スムーズに移動できます。
周辺に屋台もあるので、ゆっくり屋台を楽しみたい人にぴったり。
なお、河川敷にレジャーシートを敷いて場所取りをする場合は、早めの時間に動くのが吉。
屋台で食べ物を調達→観覧スポットへ向かう流れがスムーズです。
足立花火大会の場所取り完全ガイドはこちら!
時間・持ち物・ベストスポットまで詳しく解説しています☟
足立花火大会の打ち上げ場所は?時間・穴場スポット・場所取り完全ガイド!【2025年最新版】
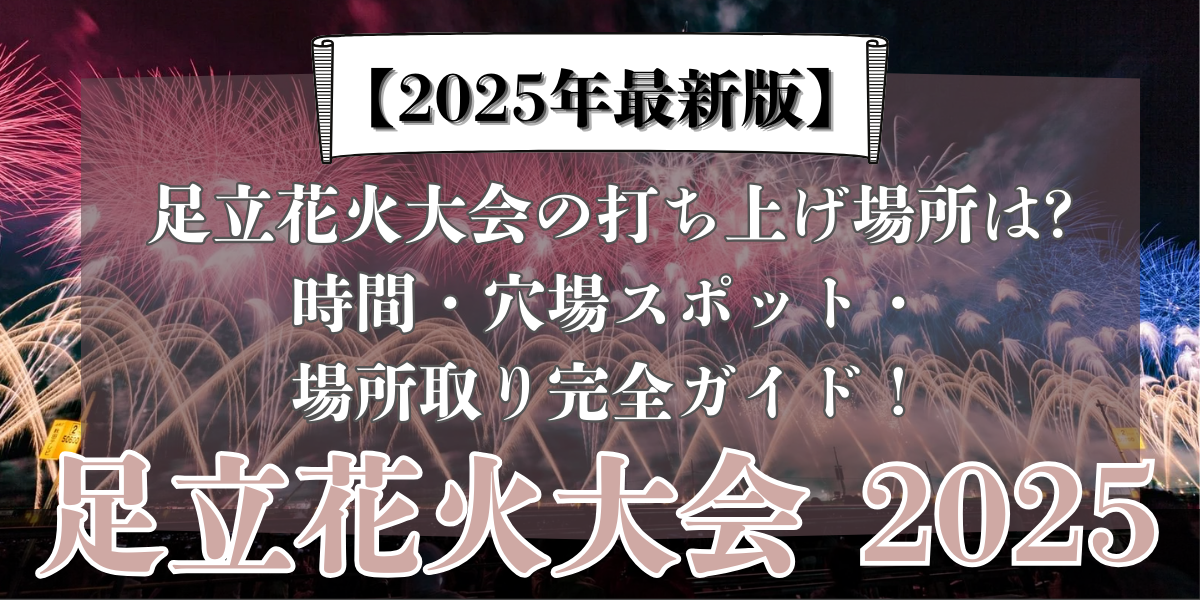
観覧場所を確保するなら?屋台との効率的な回り方
屋台を楽しんだ上で、花火もゆっくり楽しみたい!
そんな方にはこんな回り方がおススメです♪
この時間帯は屋台が本格的に営業を始める頃。
人出はまだピークではないので、人気メニューも比較的スムーズに購入できます。
▶ この時間にできること
- 混雑前にお目当ての屋台グルメをゲット!(焼きそば、かき氷、電球ソーダなど)
- 写真映えするスイーツやドリンクをゆっくり選べる
- 暑さが厳しい日は冷たいもの(かき氷・ジュース)を早めに確保するのがおすすめ
- ゆかたでお出かけする方は、人の少ないうちに写真タイムも◎
花火の打ち上げ場所近くの好スポットは早い者勝ち!
この時間に動くのが吉です。
▶ こんな準備をすると安心
- レジャーシートは必須!なるべく広めに持っていくと快適
- なるべく斜面ではなく平らな場所を探すのがコツ
- 近くにトイレや出入りしやすい道があるかもチェック
- 日が暮れるまでの間、うちわ・帽子・日傘・冷感タオルがあると快適
- 家族やカップル、友達同士でスペースを囲んでピクニック気分を楽しもう
会場に座ってから打ち上げまでは2時間以上の空き時間。
でも、それをのんびり過ごす時間も花火大会の楽しさのひとつです。
▶ 待機中の過ごし方アイデア
- 屋台グルメを食べながらピクニック気分で談笑
- スマホで写真整理やSNS投稿(充電器があると安心!)
- 軽めのカードゲームやゲーム機(ミニボードゲーム・switchなど)で盛り上がる
- 日が沈んでくると風が出て気持ちよくなります。
夕暮れの風景と共に花火の雰囲気が高まっていくのを楽しもう
この流れが、屋台も花火も満喫するベストな動き方です。
足立花火大会会場へのアクセス方法
足立花火大会のアクセス方法はいくつかあります。
最寄り駅一覧
最寄駅から会場までの所要時間とルートをご紹介!
- 北千住駅(JR・東武・東京メトロなど)
- 梅島駅(東武伊勢崎線)
- 小菅駅(東武スカイツリーライン)なども利用可能
- 五反野駅
- 西新井駅
- 北千住駅
-
JR常磐線、東京メトロ日比谷線、東京メトロ千代田線、東武伊勢崎線、つくばエクスプレス
北千住駅から約徒歩12分 - 梅島駅
-
東武伊勢崎線(東武スカイツリーライン)梅島駅から約徒歩23分
- 小菅駅
-
東武伊勢崎線(東武スカイツリーライン)小菅駅から約徒歩22分
- 五反野駅
-
東武伊勢崎線(東武スカイツリーライン)五反野駅から約徒歩21分
- 西新井駅
-
東武伊勢崎線(東武スカイツリーライン)、東武大師線 西新井駅から約徒歩32分
少し離れた駅を利用することで、混雑を避けながら屋台も楽しむことができます。
混雑回避のポイント
混雑を回避できるポイントを4つご紹介いたします!
- 最も混雑するのは北千住駅周辺
- 西新井駅や梅島駅を使うと、比較的スムーズ
- 17時前に現地到着が理想的
- 花火終了後は各駅が大混雑!→花火後は時間をつぶしてから帰るのもアリ◎
上記4つを把握しておくことで、混雑回避して花火と屋台どっちも楽しみましょう!
まとめ|道中がまるごと“お祭り通り”になる足立花火大会
- 足立花火大会では会場内に屋台は出ないものの、北千住や西新井方面のルート沿いに多数の屋台が登場
- 営業は15時〜16時頃スタート、混雑ピークは17〜19時
- SNS映えスイーツや韓国グルメなど、2025年のトレンド屋台にも注目!
早めの行動で、混雑を避けつつ「屋台グルメ×大迫力の花火」が楽しめます!
2025年の最新出店情報は、公式サイトや足立区のお知らせをチェック!
今年の5月最終日は、足立花火大会を満喫してください♪
足立花火大会についてもっと知りたい方はコチラ☟
足立花火大会の打ち上げ場所は?時間・穴場スポット・場所取り完全ガイド!【2025年最新版】